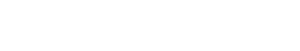「七五三って、数え年? それとも満年齢?」
「どっちでもいいって聞い他ことがあるけど、どうやって選んだらいいんだろう…」
「うちの子の七五三をいつやるべきなのか知りたい!」
ネットで調べても「七五三は数え年・満年齢のどちらでもOK」「家庭の判断で」と書かれていて、 「じゃあ、うちの子はどっちで祝えばいいの?」と悩んでしまった方も多いのではないでしょうか。
七五三は、どちらを選んでも本当に間違いではないんです。
でも、“何を基準に選ぶか”がはっきりすれば、選びやすくなりますよね。
そこでこの記事では、
など、七五三準備を安心して進められるヒントを、ぎゅっと詰め込みました。
記事の中盤では、 ”〇〇年生まれのお子様はいつ七五三をしたらいいのか?” という『七五三の年齢早見表』も記載しています!
読み終えるころには、 「うちはこのタイミングでやってあげよう」とスッキリ決められるはずです。
お子様の大切なお祝いを、ご家族皆様で気持ちよく迎えられますように願っております。
ちなみに、年間300件以上の七五三撮影をさせていただいている阿部写真館では、数え年の2歳のお子様や、体調やご家族様の事情で撮影する機会を過ぎてしまった4歳・6歳・8歳のお子様の撮影も通常通り承っております。
衣装のサイズも豊富にご用意がありますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
\ご家族さま・兄弟姉妹さまとの撮影も大歓迎!/

いつでもLINEでご相談ください
目次
七五三は何歳で祝う?いつやるのが正解?

初めて七五三を迎えるご家庭では、「何歳でやるもの?」「いつお祝いすればいいの?」と、悩まれる方も多いのではないでしょうか。
七五三は古くから伝わる行事ですが、今ではご家庭ごとに祝い方もさまざまです。
この章では、「七五三はどんな行事か」「いつ・何歳でお祝いするのか」といった基本を、分かりやすくまとめて紹介していきます。
七五三の正式な日は『11月15日』!近年は10月〜12月にお祝いされる方が多数

七五三は、本来「11月15日」が正式な日とされています。
これは江戸時代、徳川綱吉が息子の健康を祈って参拝した日が由来とされ、その後“お祝いの日”として定着してきました。
ただ、11月15日が平日であることも多いため、実際にその日に行うご家庭は少なく、今では10月中旬から12月初旬にかけて、混雑や気候、ご家族の予定に合わせて柔軟にスケジュールを組む人が多くなっています。
最近では、春や初夏にお参りされるケースも見られるようになりました。
「この日でなければならない」というルールはないので、ご家族にとって負担のないタイミングを選んでいただければ大丈夫です。
七五三は何歳で祝うの?年齢と性別による目安をまとめました

七五三は、お子さまの成長をお祝いする日本の伝統行事です。
年齢と性別によって、次のようなタイミングが一般的とされています。
- 3歳:男女ともに対象ー「髪置きの儀」が由来
- 5歳:男の子が対象ー「袴着の儀」が由来
- 7歳:女の子が対象ー「帯解きの儀」が由来
3歳の「髪置きの儀」は、本来男女どちらにも当てはまるお祝い事でしたが、現代は女の子の七五三として広く知られています。
とはいえ、「この年齢じゃないとダメ」という決まりはありません。
地域の風習やご家庭の考え方によって、年齢の選び方はさまざまです。
たとえば、「3歳と5歳の2回とも男の子をお祝いする」「兄妹の年齢に合わせて同時にする」など、ご家族の状況に合わせて柔軟に考えていただいて大丈夫ですよ。
七五三の由来は?それぞれの年齢に込められた意味

七五三のはじまりは、平安時代から江戸時代にかけて行われていた成長の儀式にさかのぼります。
当時は、幼い頃に病気で命を落とすお子様も多く、子どもの健康や無事な成長を強く願う気持ちが、今よりもずっと深かったと言われています。
以下のように、年齢ごとに意味のある節目がありました。
- 髪置きの儀:3歳から髪を伸ばし始める節目(男女ともに対象)
- 袴着の儀:5歳で初めて袴を着る節目(男の子)
- 帯解きの儀:7歳で大人と同じ帯を使い始める節目(女の子)
これらの習わしが時代とともに変化し、今の七五三という形になりました。
今でも「ここまで元気に育ってくれてありがとう」という思いを込めて、ご家族そろって神社にお参りされる方が多くいらっしゃいます。
無理にルールにとらわれず、「今のうちの子にとって良いタイミング」で、思い出に残る七五三を迎えていただけたら嬉しいです。
『満年齢と数え年』どっちで七五三を祝う?違いと選び方のポイント

七五三を迎えるにあたって、「うちは数え年?それとも満年齢で祝えばいいの?」と 迷われるご家庭はとても多いです。
かつては、七五三は数え年で行うのが一般的とされていましたが、 現在では満年齢でお祝いされるご家庭も増え、どちらも間違いではありません。
撮影スタジオでも「どちらが正しいんですか?」とご相談いただくことがよくありますが、 いちばん大切なのは、「お子様・ご家族様にとって、無理のないタイミングかどうか」です。
ここでは、数え年と満年齢『それぞれの年齢の数え方と違い』について、わかりやすく紹介します。
満年齢とは?現在広く使われている年齢の基準

満年齢は、現代の日常生活で使われている、一般的な年齢の数え方です。
生まれた日を0歳とし、その後は誕生日を迎えるごとに1歳ずつ年齢を加えていきます。
お子さまの成長のペースや体格に合わせやすいため、現在では満年齢で七五三を祝うご家庭が増えています。
撮影時にも、「着物をしっかり着られる体格になってから」「集中力がついてから」といった理由で、 満年齢のタイミングを選ばれる方が多くいらっしゃいます。
数え年とは?昔ながらの年齢の数え方

数え年とは、生まれた時点で1歳とし、以降は毎年1月1日に年齢が1つ加算されるという考え方です。
たとえば、12月に生まれたお子さまは、翌年の元日にはすでに「2歳」と数えられることになります。
こうした仕組みのため、実際の年齢(満年齢)よりも、数え年の方が1歳ほど早く七五三を迎える計算になります。
神社によっては、今でもご案内やお札の授与などが「数え年」で記載されている場合もありますので、 地域の習わしを確認しながら判断するのも1つの方法です。
満年齢と数え年はどちらを選んでもOK!ご家庭の考え方や地域性に合わせて

意外かもしれませんが、七五三は、「この年齢でこうしなければならない」という決まりごとはありません。
実際にフォトスタジオが実施したアンケート結果は以下のとおりです。
「満年齢で七五三をお祝いした」と回答した方が全体の74.5%
「数え年でお祝いした」という方は25.4%
このように、最近では満年齢でお祝いされるケースが主流になりつつありますが、 『3歳のあどけない姿を残しておきたいから数え年で』など、 ご家庭の想いを優先して選ばれるのが何より大切だと思います。
無理にどちらかに合わせようとせず、 『うちの子にとってちょうどいい時期』を見つけてあげてくださいね。
満年齢で祝うメリット・デメリット

最近では、七五三を満年齢でお祝いされるご家庭が増えています。
お子さまの成長具合やご家族の準備のしやすさを考えると、 「満年齢のほうがちょうどよかった」という声を多くお聞きします。
ただし、どんなことにも良い面・気をつけたい面の両方があります。 ここでは、満年齢で七五三を祝う際のメリットとデメリットを、わかりやすく整理して紹介します。
満年齢で祝うメリット

満年齢でのお祝いは、お子さまの心身ともにしっかりしてきた頃なので、 当日の流れがスムーズに進むというメリットがあります。
主な利点は次のとおりです。
- 衣装の着付けや撮影に協力的になりやすい
言葉の理解が進み、自分の気持ちを伝えられるようになる時期なので、着物を嫌がることが少なくなる - ヘアアレンジの幅が広がる
髪の毛の量が増えてきて、自毛でのアレンジがしやすくなる - 体格が安定してきている
レンタル衣装のサイズが合いやすくなり、選べるデザインも豊富に。お気に入りの衣装も見つかりやすい
とくに3歳の七五三では、2歳と比べて心も体もグッと成長している時期なので、 「思ったよりもスムーズに撮影ができました」というご感想をよくいただきます。
満年齢で祝うデメリット

一方で、満年齢ならではの注意点も。
「もう少し幼い姿を残しておきたかったな…」と感じられる方がいらっしゃるのも事実です。
- あどけなさが薄れる
3歳の女の子は、2歳に比べて顔つきや雰囲気がしっかりしてくるため、「幼さ」がやや減って感じられることも - 衣装のサイズに限りが出る可能性
体格がしっかりしてくる分、特に7歳など大きめサイズのレンタル衣装には在庫が少ないケースも
希望の衣装が着られないことがあるため、早めの衣装チェックが重要!
成長が早めの7歳さんは、数え年を検討しても良いかもしれません。
数え年で祝うメリット・デメリット

数え年で七五三をお祝いするのは、もともと日本の伝統的な習慣に基づくスタイルです。
現在でも、神社の案内や地域の風習では数え年が基準になっている場合があり、 昔ながらの形式を大切にされるご家庭では、今も根強く選ばれています。
また、「同じ学年のお友達と一緒にお祝いしたい」「兄妹でタイミングを合わせたい」といった理由から、 数え年を選ばれる方も少なくありません。
ただし、実年齢がまだ幼い段階でのお祝いとなるため、 お子さまへの負担をしっかり考慮することが大切です。
数え年で祝うメリット

数え年でのお祝いならではの魅力があります。
特に「この時期だからこそ見られる姿を残したい」というご家族にはぴったりです。
- あどけない幼さを写真に残せる
まだ幼さの残る表情や、たどたどしさなど、“今だけの瞬間”をしっかり記録できる - 同級生と同じタイミングで祝える
園のお友達と話題が合いやすく、行事やプレゼントのタイミングなどもそろえやすい
数え年で祝うデメリット

一方で、数え年ならではの難しさもあります。
特に2歳のお子様は、ちょっとしたことで気分が変わりやすく、撮影やお参りが思うように進まないことも。
- イヤイヤ期と重なる可能性
3歳のお祝いを数え年で行う場合、実年齢はまだ2歳
着物を嫌がったり、撮影中にぐずってしまうことも - 髪の長さや量が足りないことも
まだ髪が伸びきっていないお子さまも多く、希望のヘアスタイルができなかったり、アレンジの幅が限られることがある - 衣装サイズが合いにくい
体がまだ小さく、平均的な3歳用の衣装では大きすぎることも
レンタル衣装の選択肢が限られるケースがある
成長スピードは個人差が大きいので、お子様の様子を見ながら「このタイミングなら大丈夫!」と感じられる時期にお祝いをしてあげられるといいですね。
お子様が『着物を嫌がって着てくれない時の対処法』については、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
七五三の年齢早見表<2025年〜2027年>

七五三の年齢計算は、「11月15日」を基準日として、11月15日に『満年齢で◯歳』という考え方をするものです。
そのため、『11月14日』生まれのお子様と『11月16日』生まれのお子様とでは、満年齢でお祝いするお子様の年齢が1つ異なることに。
しかし、この考え方は大変ややこしくて難しいので、一目でわかる『七五三の年齢早見表』を用意しました!
お子さまの生まれ年と照らし合わせながら、 七五三がいつになるのかをチェックしてみてくださいね。
【2025年の七五三】
年齢 | 満年齢 | 数え年 |
3歳 | 2021(令和3)年11月16日〜2022(令和4)年11月15日生まれ | 2023年(令和5年)生まれ |
5歳 | 2019(平成31/令和1)年11月16日〜2020(令和2)年11月15日生まれ | 2021年(令和3年)生まれ |
7歳 | 2017(平成28)年11月16日〜2018(平成29)年11月15日生まれ | 2019年(平成31年/令和1年)生まれ |
【2026年の七五三】
年齢 | 満年齢 | 数え年 |
3歳 | 2022(令和4)年11月16日〜2023(令和5)年11月15日生まれ | 2024年(令和6年)生まれ |
5歳 | 2020(令和2)年11月16日〜2021(令和3)年11月15日生まれ | 2022年(令和4年)生まれ |
7歳 | 2018(平成29)年11月16日〜2019(平成30)年11月15日生まれ | 2020年(平成30年)生まれ |
【2027年の七五三】
年齢 | 満年齢 | 数え年 |
3歳 | 2023(令和5)年11月16日〜2024(令和6)年11月15日生まれ | 2025年(令和7年)生まれ |
5歳 | 2021(令和3)年11月16日〜2022(令和4)年11月15日生まれ | 2023年(令和5年)生まれ |
7歳 | 2019(平成30)年11月16日〜2020(平成31年/令和1年)年11月15日生まれ | 2021年(平成31年/令和1年)生まれ |
※地域によって風習や神社の案内が異なる場合があります。
お参り予定の神社がある場合は、事前に確認しておくとより安心です。
七五三の年齢を決める判断基準3つ

「数え年と満年齢、どっちでもいいのはわかったけど、結局どっちがいいの?」と悩まれる方はとても多いです。
決まりがない分、迷ってしまいますよね。
そこここでは、スタジオ現場でもよくご相談をいただく、七五三の年齢を選ぶ際の判断基準4つを紹介します!
衣装のサイズと子どもの体格

とくに3歳の七五三の場合、数え年だと実年齢は2歳。
体格が小さめのお子様だと、レンタル衣装のサイズが合わない場合もあります。
七五三用の着物は、平均的な3歳児の体格で作られているため、2歳児には大きすぎて、だぼついてしまうケースが多く、小さいサイズの衣装はデザインが限られがち。
「この着物を着せたい」と明確なイメージがある場合や、サイズが不安な場合は、 満年齢でのお祝いのほうが安心です。
兄弟姉妹とのタイミングを合わせる

兄弟姉妹がいるご家庭では、七五三を同時に行うことで準備や費用をまとめられるメリットがあります。
たとえば、
- お兄ちゃんは5歳(満年齢)
- 妹は3歳(数え年)
というように、年齢の数え方を調整しながら、同じタイミングでお祝いするご家庭も多いです。
一緒に撮影することで「きょうだいの思い出」も残せますし、 ご家族のスケジュール調整・金銭面での節約がしやすくなるのも嬉しいポイントです。
子どもの発達段階をふまえて考える

2歳〜3歳ごろのお子さまは、気分や体調が大きく影響しやすく、日中のリズムが定まっていないこともあるでしょう。
- イヤイヤ期と重なりやすく着物を嫌がることがある
- お昼寝や空腹でご機嫌が崩れやすい
- トイレトレーニング中で、着物着用中のトイレが大変
ぐずりやイヤイヤは、お子さまだけでなくご家族にとっても負担になる場合もあります。
「今なら落ち着いてお祝いできそう」「まだちょっと早いかも」といった、ご家族様の感覚を大切にして、無理のないタイミングを選びましょう。
残したいお子様・家族の姿から考える

満年齢ではまだ2歳でも、「この幼さを残しておきたい」「兄弟とタイミングを合わせたい」と、 数え年の3歳(実年齢2歳)で七五三を迎えるご家庭もあります。
体力や気分に左右されやすかったり、衣装や髪型が制限される可能性もあるといった注意点もありますが、無理のない形で準備すれば、 「やってよかった」と思える素敵な記念になるでしょう。
3歳女の子の和装・洋装ヘアアレンジについては、ぜひこちらを参考にしてみてください。
七五三の記念撮影は『前撮り』『当日撮り』『後撮り』から選べる

七五三といっても、お祝いの形はご家庭ごとにさまざまです。
お子さまの性格や年齢、ご家族のスケジュールに合わせて、 無理なく楽しめるスタイルを選んでいただくのが1番。
七五三の記念撮影は、『前撮り』をする方もいらっしゃれば、お参りと同じ日に『当日撮り』を選択する方も。
ご家族様の都合や体調などで撮影ができなかった場合には、『後撮り』という選択肢もありますよ。
数え年で「まだ落ち着いて撮影するのは難しいかも…」と感じる方は、お参りは『数え年』、記念撮影は『満年齢』でするのもおすすめです。
それぞれ、前撮り・当日撮り・後撮りもメリットとデメリットがありますので、お悩みの方はぜひこちらの記事も参考にしてみてくださいね。
まとめ

七五三は、数え年でも満年齢でも「ご家族に合った形」で祝うことが、何より大切です。
お子さまの性格や体格、ご家族の予定などに合わせて、無理なく笑顔で過ごせるタイミングを選んでみてください。
写真だけでも、お参りだけでも、2回に分けてのお祝いでも構いません。
決まりにとらわれず、「わが家らしい七五三」にしてあげてくださいね。
「まだ2歳だけど大丈夫?」「もう8歳…今さら間に合うかな?」と不安に感じている方も、ご安心ください。
お祝いのタイミングに“早すぎる”“遅すぎる”はありません。
今しか見られない表情、今だけの子どもらしさ。
その“かけがえのない今”を、どうか大切に残してあげてくださいね。
年間300組以上の七五三を撮影させていただいている阿部写真館では、衣装のこと、スケジュールのこと、お子さまのご様子に合わせた撮影の工夫まで、丁寧にサポートいたします。
「色々迷ってしまって…」という段階でももちろん大丈夫です。
“お子様の今”、その一瞬を、楽しい思い出としてカタチにできるよう、心を込めてお手伝いさせていただきます。
LINEからお気軽にご相談ください。
\年齢を気にせず七五三撮影を楽しみましょう♪/
いつでもLINEでご相談ください